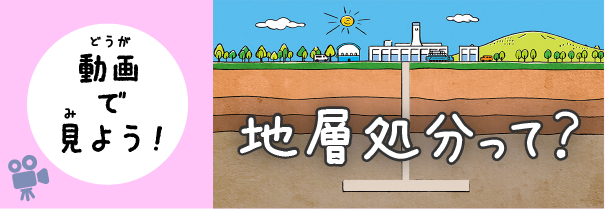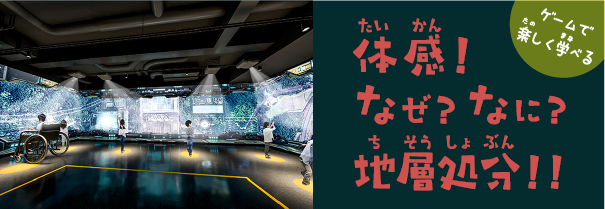地層と化石
~地層の年代を調べてみよう~
教えて博士!

化石からは、さまざまな情報が得られるよ。例えば、ある限られた時期にしか生息していない動物や植物の化石が見つかる地層は、地層が堆積(たいせき)した時代が特定でき、また離れた地域に分布する地層を結びつける手がかりにもなるよね。こういった年代の特定に役立つ化石を「示準化石」(しじゅんかせき)と呼ぶんだ。また、化石の特ちょうによってその当時の気候が今よりも暖かかったとか、水深が深かったということも推定できる場合がある。このように、地層が堆積(たいせき)した当時の環境(かんきょう)の推定に役立つ化石を「示相化石」(しそうかせき)と呼ぶよ。
例えば、琥珀(こはく)は樹液(じゅえき)が化石になったものだから、琥珀が見つかるところは昔、木が茂っていた場所だったということがわかるんだ。ちなみに、琥珀が見つかるということは、そのあたりには木の化石である石炭もでてくる可能性があるよ。

具体的に、岩石や地層・化石の年代を特定する方法としては、放射年代測定という方法があるんだ。同じ元素の中にも不安定なものが含まれていて、一定のスピードで半分ずつに減っていく(半減期)。この半減期は元素毎に決まっている。例えば、炭素はふつう原子量が12(6個の陽子と6個の中性子)という炭素12(12C)だけれど、中性子が2つ多い炭素14(14C)というのが少しだけ存在している。大気中に含まれる12Cと14Cの割合は一定だから、生きている時に動物や植物が内部に取り込んでいる14Cの割合は大気と同じだよね。でも死んで化石になると新たに取り込めないので、不安定な炭素14(14C)は一定の半減期で安定したチッ素14(14N)に変わり、減っていく。このため、動物や植物の化石や、それら化石を含む地層の場合、12Cと14Cの割合を調べることで年代が推定できるんだ。14Cの半減期では調べられないもっと古い年代については、別の半減期を持つ元素を利用して調べる方法もあるんだ。
また微化石(びかせき)といって、数ミリメートルから数マイクロメートルの小さな生物の化石も年代特定に大きな役割を果たしているよ。例えば、マツやコナラの花粉や、珪藻(けいそう)や放散虫(ほうさんちゅう)などがある。時代により大量に存在していれば、それは示準化石として年代を特定することができたり、また環境(かんきょう)によって生息する種類も異なることから、示相化石の役割を果たすこともあるんだ。
これらの調査やまわりの地層との比較など、さまざまな情報を組み合わせて、地層や化石の年代を特定するんだ。